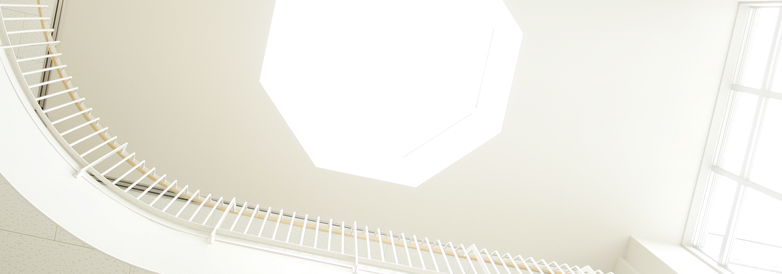Q&A 高校教職員版 学園概要
Q&A 高校教職員版
各部局で暗号化USBメモリを用意(配付)してください。教育職員は教育研究費で購入してください。暗号化機能のないUSBメモリを利用する際には、データファイルを暗号化するか、パスワードをかけてください。
個人情報や学園で知りえた情報を、許諾を得ず、むやみに公開したり、口外しないよう、誓約書を用意し、出入り口でサインをさせてください。
原則禁止です。持ち出しが必要な場合には管理者に申し出てください。
印刷物については、他の教職員に回覧する場合、回覧後、作成者が回収する等して、一括してシュレッダーにより処分してください。作成者本人のみが使用する場合には、活用後にシュレッダーにより処分してください。また電子データも活用が終了した時点で消去してください。各部局で年度や学期単位で消去日を決めるとよいでしょう。
ビデオ撮影を希望する人に、撮影対象、撮影時間、撮影場所、利用目的(情報共有の範囲)、保存期間、情報削除等について説明する文書、撮影依頼書を提出させてください。また、誓約書(同意書)を交わし、それらの文書や誓約書(同意書)は、最低でも撮影対象になった園児・児童・生徒の卒業時までは保存しておいてください。なお、撮影対象の保護者への許諾については、年度のはじめに、ビデオ撮影等に関して保護者に説明して許諾をとる(これをオプトインと言います)と効率的です。ただし、後日、やはりビデオ撮影はしないでほしいという要望があった場合には、該当対象者についてはビデオ撮影はできません。この場合、すでに当該対象者を撮影し、公開している映像は削除が必要になる場合があります(これをオプトアウトと言います)。※学級通信、広報、ホームページに掲載する写真等についても同様です。
コンピュータシステムに限らず、社会のあらゆる制度やシステムに絶対に安全である(ゼロリスク)ものは存在しません。必ずリスクがあります。パスワードの管理や機器管理等をしっかり行ってください。
校務、教務、事務用に使用しているパソコンは教室では使用しないでください。授業用パソコンと校務用パソコンは別のものとするのが一般的です。また授業用パソコンには秘匿すべき個人情報(成績等)は保存しないでください。
園児・児童・生徒(保護者)に許諾を得ることが先決です。一人でも許諾を得られないならば発表できません。そのため、近年はこのような情報は発表しない傾向にあります。進路情報等も同様で、不用意に発表したことにより、謝罪に追い込まれ、新聞沙汰になった例もあります。ただし、教育としてどうしても必要な措置と考えるならば、職員全員でこうした発表について議論を行い、方針を決め、園児・児童・生徒(保護者)に理解を求めるべき(合意形成するべき)です。
学級通信など、学校が園児・児童・生徒に配付する文書は「公開されるもの」と考えてください。したがって、公開してよいものを掲載してください。感想文等を掲載する場合には、必ず本人及び保護者の許諾を得てください。
開示請求があった場合には伝えなければいけません。
教職員は、学園と守秘義務契約を結んでいると見なせます。したがって、会議資料の議題、事案は、それが公表される以前にSNS等への情報掲載はできません。また、個人の写真や情報を掲載する際には、本人から許諾を得てください。法人や個人の名誉や人権を毀損しないよう配慮し、批評を超えた誹謗中傷、暴言の書き込みは控えてください。なお、たとえ真実の情報を書き込んだとしても、名誉毀損罪は成立します。
量に関わらず個人情報が記載された用紙等は必要がなくなった時点(評価終了等)で、シュレッダーまたは溶解処理により処分してください。
校務や教務(成績処理や名簿処理等)は個人のパソコンでは行わないようにしてください。授業用教材の作成や掲示等の使用に限定してください。
大学で指導はしていますが、学校側でも指導をして下さい。たとえば、実習開始時に、実習で知りえた情報を口外しない、置き忘れや紛失に注意をするよう必ず注意喚起してください。また、実習生と守秘義務契約を交わし、誓約書にサインをさせるなどして実習生の情報保護意識を高めてください。
クラウドが特段にセキュリティが甘いわけではありません。他のパソコンソフトウェアやサービスと同じように、パスワードの管理、機器管理、ウィルス対策をしっかり行ってください。
内容や程度に関わらず、一つでも個人情報が記載されていればシュレッダーまたは溶解処理により処分してください。
児童生徒のUSBメモリは、ウィルス感染リスクを高めます。学校のUSBメモリを一時的に児童生徒に貸し与えるか、あるいは、電子メール等でのファイルの受送信のほうが安全です。
保護者の許諾が必要です。その必要性を十分に説明し、保護者と同意のもとにやりとりをしてください。どうしても許諾が得られない児童生徒(保護者)は、保護者の指定の方法で連絡してください。
原因は個人によって異なります。スクールカウンセラーや養護教諭に相談し、アセスメントを行うなどして、児童生徒、担任教員、保護者が協力して指導にあたってください。保護者には、ネット利用のルールを決める等、家庭での生活管理をするように促してください。万が一、重大な依存症状が認められる場合には、保護者と面談の上、医療機関に相談するように促してください。
電子メールは、その内容に個人情報が含まれる場合には配慮が必要です。まず、電子メールアドレス自体も個人情報です。宛先やCC欄に、複数の電子メールアドレスを入力して送信すると、それだけで個人情報が漏えいしたことになります。複数の電子メールアドレスへの送信が必要な場合には、BCC欄に電子メールアドレスを入力して送信してください。また、ファイルを開封するためのパスワードを電子メールで送信することは推奨されません。しかし、便宜上、どうしても電子メールでのパスワード送信が必要な場合には、ファイルとは別途のメールで送信してください(これは極力避けてください)。